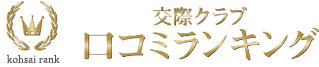さあ、正しく焼き魚に向き合おう

焼き魚が食べられるのは大和撫子の象徴
普段の生活でもなかなかきれいにいただけない焼き魚。
そんな焼き魚が、ちょっと高級なお店でぽんっ!と出てきた日には筆者をはじめとして困ってしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
会席料理においても焼き魚は「お箸の使いかたや食べかたが最も求められる料理」です。
今日から美しい食べかたを練習していくためにも、焼き魚の正しいいただきかたを今回の記事で覚えてしまいましょう。
柑橘類と生姜、同じ「トッピング」だと思っていませんか?

焼き魚(切り身・尾頭付問わず)が出されたとき、スダチなどのかんきつ類や、薄紅色の細長い生姜やレンコン(いわゆる”はじかみ”)がついている場合も多いと思うのですが、みなさまはどう対処していますか?
この柑橘類とはじかみ、一緒に盛り付けられて出されてきますが、それぞれ目的が違うものです。
- 柑橘類 お魚をいただく「前」に絞り汁をかけるためのもの。これは魚に酸味や香りを加えた方が美味しく食べられるためで、そのために塩が若干強めになっている場合もあります。
- はじかみ お魚をいただいた「後」に生臭さを消すために口直しとしていただくもの
です。
ですから、お魚が運ばれて来たらまずはじかみには手を付けず、柑橘類の皮の部分を右手でつまんで魚に絞りましょう。
このときに周囲に果汁を飛ばさないように左手を添えるのがマナーです。
絞り終わった柑橘類は皿の上側に置きます。
はじかみはお魚の生臭さを消すための食べ物なので、お魚をいただいた後に楽しみましょう。
生姜は懐紙で口元を隠しながら根元の部分をいただきます。
お魚は「ひっくり返さない」。

お魚も基本的に「食べやすい大きさにお箸で切って」いただくのが基本です。
会席料理の場合、ほとんどは切り身の状態で出てくるので、左側から一口ずついただきます。
尾頭つきの状態でお魚が出てきた場合は、必ず頭が左、お腹が手前の状態で出されますので、まずは左側から尾の部分に向かっていただきます。
頭のほうからいただく理由は、魚の身の構造上、頭の方から食べると骨の身が外しやすいからです。
表面をすべていただいたのちに裏側をいただくのですが、このときに
- お魚をひっくり返して裏側の身をいただく
- 骨の間にお箸を入れて裏側の身をいただく
という事態は避けたいものです。
正しいいただきかたは、「そのままの状態で箸を骨の下に差し入れて骨を外してお皿の向こう側(上側)において下の身をいただく」です。
頭の部分を懐紙(ない場合は左手で軽くおさえる)などで押さえて動かないようにするとスムースに外すことができます。
お魚の皮は残しても”失礼”にはあたりません。
小骨などが口に入ってしまったら懐紙や左手で口元を覆って、指先で取り出して柑橘類を絞ったものと一緒にお皿の隅にまとめておきましょう。
残骸をまとめたものが「汚いな」と感じたら懐紙を上にかぶせておきましょう。
今回はお魚のいただきかたについておさらいしてみましたがいかがでしたか?
かなり文章で説明するとあっさり終わってしまうものですが、実践してみるととても難しいのが焼き魚の難しいところ。
イワシやサンマで日ごろから練習してみてはいかがでしょうか。
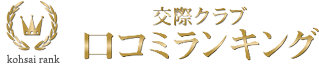


 #1564 (loading title)
#1564 (loading title)



 コンソラトゥール
コンソラトゥール