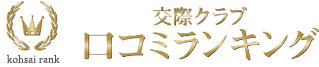出来ないなんて恥ずかしい、お箸の基本

唐突ですがみなさまは、普段から食事で使うお箸、しっかり使いこなせていますか?
持たない日はないというほど慣れ親しんでいるお箸ですから「いくらなんでも箸ぐらいはちゃんと使ってるよ!」という方もたくさんいらっしゃるでしょう。
しかし、箸には思いのほかたくさんの「ルール」があります。
覚えておくと和食だけではなく中華料理や韓国料理、更には一部の東南アジア料理でも使える知識もあるので今回はさっとお箸のマナーをおさらいしてみましょう。
なお今回の記事では主に和食のマナーを想定してお話を進めていきます。
知ってた?お箸には「持ち上げかた」もある

お箸の「正しい持ち方」は日本人であれば多くの方が慣れ親しんでいるものかもしれませんが、みなさまお箸に「持ち上げ方」というものがあることをご存知でしたか?
お箸の持ち方の基本は「三手」と呼ばれています。
まず右手でお箸の真ん中あたりを上からすこしつまんで持ち上げます
つぎに左手を下から添えて、その間に右手を端に滑らせるように移動します。
上からお箸を持っていた右手を下に滑らせるように添えて正しい位置でお箸を持ちます。
これを普段のご家庭の食卓から行っているという人は少数派かもしれません。
筆者も家ではやっていないのですが…家で実践してみたところ「ひょいっ」と持ち上げてしまうより見栄えが非常によくなります。
ひとりぐらしの淑女のみなさまでしたら、「大きい鏡の前で食事をする」と一挙手一投足のビジュアルが確認できるのでおすすめです。
顔の前で左右に割り箸を割るのはNG
また、お箸を使う前に心得ておきたいもうひとつのポイントが割り箸の割りかた。
恋人の前や、目上の人と食事をするシーンで割り箸を割るとき、割り箸を縦にもって左右で割っていませんか?
「パキッ!…あ、ごめんなさい!」
…そうなる前に、正しい割りかたを覚えておきましょう。
正しい割り箸の割りかたは、「膝の上」で「上下」に割るです。
これができるだけでもかなり周りの人の反応が変わってきます。
また、なかなかご家庭では使わないかもしれない箸置きですが、こういった場ではぜひフル活用したいものです。
箸置きが万一提供されなかった場合は、箸の袋の上に箸を置いたり、箸置きを折りましょう。
無意識にやってない? お箸のご法度「○○箸」をまとめてみました。

ここまではお料理をいただくまでのお話でしたが、ここからが本番です。
基本的なことから「え、それもだめなの?」と人によっては思ってしまうものまで、食事のときの「嫌い箸(無作法)」をまとめてみました。
- ねぶり箸 箸についたものを舐めとる行為
- 箸渡し 箸と箸で食べ物のやり取りをする行為(死者の骨を拾うのと同じ動作は縁起が悪い)
- 空箸 一度食べようとして取った食べ物を元に戻す
- 握り箸 箸を握りしめて持つ
- 二人箸 食器の上で2人同時に同じ料理を挟むこと
- 刺し箸 物を刺して食べること
- 迷い箸 どれを食べようか迷ってあちらこちらに箸を巡らせる行為
- 指し箸 人や物を箸で指すこと(※刺し箸とは別物)
- 立て箸 箸を立てること
- 探り箸 汁物の具を箸で探ってえり好みすること
- 重ね箸 ひとつのものばかりを食べること
- 噛み箸 箸の先を噛むこと
- 移り箸 一度取ろうとしたものから他に箸を移すこと
- 涙箸 箸の先から水滴を落とすこと
- 渡し箸 食器の上に箸をまたがせること(※これは「もう要りません」の意)
- 違い箸 違う箸を1本ずつつかうこと
- かきこみ箸 お茶碗を口に当てて、箸で中のものを掻き込む食べ方
- 寄せ箸 食器を箸で移動させること
- 叩き箸 まさに下の図
☆ チン
☆ チン 〃 ∧_∧
ヽ___\(\・∀・)
\_/ ⊂ ⊂_)
基本的なものや「まさかそれはしないでしょ」というものもありますが、ついつい箸置きを使っていないご家庭では、悪いとわかっていつつ渡し箸をしてしていませんか?
また、お箸を使うときは基本的に「箸先五分(1.5㎝)、長くて一寸(3㎝)」という言葉があります。
箸先の汚れはその程度の長さにとどめましょうという意味です。
かなり短いなあ……と筆者も思いましたが、これは箸使いから一口の量に至るまでかなり鍛錬が必要です。
お箸をおくときや食べ終わった後も気を抜くのはNG
食べるときは及第点でも、「家に帰るまでが遠足」と同じように、「片づけるまでがお箸」です。
手からお箸を離すときは必ず箸置きの上、箸置きが用意されていない場合は、お盆の左側の淵に箸先をかけましょう。
お食事が終わったら箸袋や四つ折りの懐紙で汚れた箸先を包みましょう。
今回は基本的なお箸の使い方を記事にまとめてみましたがいかがでしたか?
和食や中華にはより細かいルールはありますが、ひとまず箸の使いかたができていれば他のことを覚えるのもスムーズです。
明日から、といわず今日の次のお食事から、お箸のマナー、もう一度気遣ってみませんか?
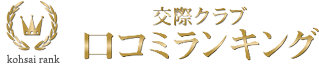


 #1564 (loading title)
#1564 (loading title)