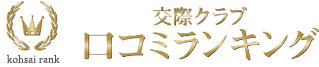わかっているだけで断然違う、正しいみそ汁のいただきかた。

格式高い料亭で和食をいただく。
ただでさえちょっと自信がない中でも最も不安を感じるのが「椀物」ではないでしょうか。
椀物とは?お酒や前菜(先付)をいただいたあとに口の中をすっきりさせるために出される汁物のことです。
季節感のあるやはり「いただくのがもったいなさそうな」お吸い物などが良く出てきます。
器のもちかた、ふたの開け方、いただきかたから食べた後まで、椀物はもっとも「和食らしいマナー」が要求されるイメージがありますが、完璧に頂くことができたらかっこいいですよね。
そこで前回の前菜に引き続き、今回は椀物のいただきかたについてお話しさせていただきたいと思います。
最初の難関「ふたの開け方」

筆者が幼いころ、両親にはじめて和食に連れていってもらったとき、いちばんはじめに衝突した問題がこれです。
「蓋があかない!」
当時の筆者は癇癪持ちでしたので、水蒸気で椀物の蓋があかないと思うやすぐさま
「開かないー!うわーん!(大泣き)」
と両親だけではなく周囲の方々の手までも非常に焼かせてしまったのですが……
ここまでではなくともみなさまの中には「椀物の蓋がうまく開けられない」という場面に遭遇した方もいらっしゃるのではないでしょうか。
椀物は、左手でお椀の淵をしっかり抑えながら、右手で蓋を少し上げるのが基本です。
しかし、このときに「なかなか蓋が離れない」という場合、右手で椀の”糸底(でっぱりの部分)”をつまんで空気を入れるように軽くたゆませましょう。
それでも蓋が離れない場合は、給仕さんにお願いしても大丈夫です。
蓋と椀を離すことができたら、右手でそっと「の」の字を書くような気持ちで静かに開きます。
そのときには蓋から滴を垂らさないように気を付けましょう。
たれそうになってしまったら、蓋を完璧にお椀から離してしまう前に、蓋をお椀の右ふちに立てかけて滴を椀の中に落としましょう(「露きりの所作」といいます)。
ここまでしっかりできても最後に迷ってしまうのが「開けた蓋はどこにどうやっておけばいいの?」というポイント。
「お膳(お盆)の外の右側」に、「両手を添えて」、「裏返した状態」で置きましょう。
蓋の外側を上向きにして置いたり、お椀に立てかけておくのはご法度です。
また、料亭で出される椀物の蓋の内側には、季節感のある蒔絵などが描かれていることが多いので、鑑賞してからいただくと和食の楽しみが倍増します。
また、椀物が出されたとき蓋が少し濡れていることがありますが、これは「器の中身にはきちんと料理が入っていますよ」と確認した印なので、気にすることはありません。
よくやりがちな「箸と椀を同時に持つ」はNG
蓋を開けるだけでもかなりのマナーがあった椀ものですが、いただくときにもマナーがあります。
- まず両手でお椀を持ち、出汁を味わいます。
両手でお椀に手を添えるときも、「右手が上位」の考え方なので、まずは右手から添えてそのあと左手を添えるようにしましょう。 - 中の具をいただくときは、まず両手でお椀を持ち、左手でお椀を持ったまま右手で箸を持ち上げて左手の小指と薬指の間に挟みます。
- 右手で箸を下から持ち替えて、左手でお椀を持ちながら中の具をいただきます。
椀物の具の中の貝は身だけを食べて、殻はそのまま椀の中に残していただくのが正解です。 - 箸を置くときには逆に、左手の小指に箸を挟み、右手を持ち替えて上から箸を持つようにし、箸置きに置きます。
「ものを大切にする」という気持ちを表すために、和食ではモノは両手で取るのが基本です。
家で食べるときについついやりがちな「お箸とお椀を同時にもつ(片手で)」のはご法度ですから、器を持つときには、お箸は一度箸置きに置くようにしましょう。
また、持てない大きさのお椀の場合は、蓋を受け皿として使ってもよいとされています。
「食べ終わってから」が椀物の勝負どころ
おいしくいただいたあとの椀物、みなさま蓋はどうしていますか?
- 食べたときそのまま
- 蓋をひっくり返して重ねる
- 蓋をずらして重ねる
実はどれも不正解で、「食べる前の状態に戻しておく(重ねておく)」のが正解。
特に蓋を逆さにして重ねると、椀物の湿気などで漆器を傷めてしまうこともあるのです。
和食はお料理だけではなく器にも気を配る料理なので、料亭側からしてみてはたまったものではないのです。
交際クラブの男性会員のような富裕層もこのような細かいマナーをきっちり見ています。
「食べ終わりましたよ」ということを第三者からわかるように配慮する必要はないので、きた時と同じように蓋をしましょう。
今回は椀物をいただくときのマナーについてお話しさせていただきましたがいかがでしたか?
いただくまえからいただいたあとまで、なかなか気を抜けない椀物ですが最初から最後まで完璧にいただけたらとても魅力的な女性に見えるのではないでしょうか。
次回はお刺身(向付)のいただきかたについてお話する予定です。どうぞご期待ください
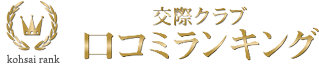


 #1564 (loading title)
#1564 (loading title)



 ニューウェーブ横浜
ニューウェーブ横浜 アート企画
アート企画